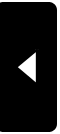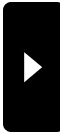2012年04月15日
バーズでリーディングカフェ

4月13日、アドバイザーをしております岡部町のバーズで
劇団spacの俳優、奥野晃司さんをお招きしてお茶を飲みながら
「ペール・ギュント」の台本の読み合わせをする、リーディングカフェ
が催されました。南米公演からお帰りになってまもなくのこのイベント。
いろいろ、お国によって笑うところが違うということ、また、関西と関東とでは
声のトーンが違ってくることなど、なるほどなと思うお話が聞けました。

ペール・ギュントや作者のイプセンの生い立ちや背景など、
大変興味深いお話を交えた、奥野さんの楽しいお話を聞きながら
台詞の読み合わせをしました。

さすが舞台俳優さんだけあって、声がすばらしい!
そして説得力のあるお話。
文字の音読がいかに難しいか熟々感じたのと同時に、
その場面の情景をイメージしながら声を出す難しさを感じました。

NHKの取材も受けました。
2012年02月18日
LAS TAPASさんで ストウブを使ったバスク料理 お食事会

3/14 LAS TAPASさんでのお食事会のメニューはこちら!
★ ランチ ¥3,500
前菜:シャルキュトリー (バスク豚のサラミ イベリコ豚のサラミ ハモンイベリコ イディアサバルチーズ ケイパーベリー 牛肉のカルパッチョ)
ピぺラードのオムレツとパン
STAUB料理: フランス側バスク郷土料理 「Soupe de Garbure」 スープ ド ガルビュール
(バルバリー鴨と(キントア)バスク豚で出汁を取り白いんげん豆に(シューフリゼ)チリメンキャベツ ソーセージ ベーコン 白いんげん豆 人参 じゃが芋)
サラダ:メリメロサラダ
デザート:マミヤ(バスクのプリン)
飲み物:コーヒー 紅茶 エスプレッソ
★ ディナー ¥5,000
前菜:シャルキュトリー(バスク豚のサラミ イベリコ豚のサラミ ハモンイベリコ 野生鹿のパテドカンパーニュ バスク産羊チーズ・イディアバルにメンブリージョのコンフィチュールを付けて)
鱈と茸のオムレツ
STAUB料理: フランス側バスク郷土料理 「Soupe de Garbure」 スープ ド ガルビュール
(バルバリー鴨と(キントア)バスク豚で出汁を取り白いんげん豆に(シューフリゼ)チリメンキャベツ ソーセージ ベーコン 白いんげん豆 人参 じゃが芋)
サラダ:田舎風サラダ (具沢山のサラダ)
肉料理:プーレ・バスケーズとライス (フランス側バスクの郷土料理)
デザート:バスクのお菓子 マミヤと焼き菓子
飲み物:コーヒー 紅茶 エスプレッソ
※メニューは変更になる場合がございます
別料金にてバスクの地酒チャコリ(微発泡白ワイン)やバスクのBioワインも
ご注文いただけます。
写真はstaubを使ったお料理「Soup de Garbure」です。お楽しみに。
イベント詳細はコチラ
ご予約お待ちしております。

2012年02月17日
LAS TAPASでバスク料理を

アドバイザーのお手伝いをしている家具Shop baseSでは、
10月にご好評をいただきましたstaubを使ったお食事会の第二弾を
3月に開催いたします。
今度はstaub × バスク料理。
静岡市内のバスク料理店「LAS TAPAS」様にご協力いただき、
ランチとディナーの2回開催です。
バスク料理とは、フランス南西部とスペインにまたがるバスク地方の伝統的な料理。
今回はTXOKO(チョコ)スタイルでお楽しみいただきます
※チョコスタイルとは…人が集まって一緒に料理をし大皿で取り分けて食べるバスク地方の文化

開催日時:3月14日(水)
ランチ 12:00~14:30 ディナー 18:30~21:00
場所:LAS TAPAS 静岡市葵区紺屋町4-22 ソワーレビル3階
参加費:ランチ ¥3,500 ディナー¥5,000
定員:各回20名様 (定員になり次第〆切り)
バスク料理のお話とお土産つきの他、ご参加いただいた方にはstaubを
特価にてご購入いただけます。
また、3/14はLAS TAPASにbaseSの家具を持ち込み、少しいつもとは
違った雰囲気の中お食事いただきます。
ご予約、お問い合わせはbaseSまで。
TEL:054-648-3113
2012年01月17日
第6回 静岡の魅力 フォトコンテスト

2012年1月15日,「第6回 静岡の魅力 フォトコンテスト」の表彰式が
グランシップにて行なわれました。
思いがけず入選を頂きました。
応募した写真はこのブログの過去の記事にほぼ同じ瞬間に撮った何枚かの
中の一枚がありますので参考までに。
審査員には大竹省二さん、山本信也カントク、沼田早苗さん、織作峰子さん
などなどがつとめてくださり、作品の批評をしてくださいました。
山本カントクが「この中で、なんで私が・・・と、思いがけず
受賞しちゃった・・・と、思っている方、ちょっと手を挙げていただけますか・」
と言う言葉に、私ともう一人の男性がそっと手を挙げました。
するとカントク
「まーぁ・・・世の中には正直な方がいるもんですねぇー」 (笑,笑・・・)
無欲だったんでしょうね。
賞を狙ったら力がこもるし、それが画面に出て来るし・・・
そう、いつものことですが、今年も「無欲」で「一生懸命」でいきましょうか・・・
HP : Atelier M's
2011年04月06日
オランダから
この度の東日本大震災の被害に遭われた方々には心からお見舞い申し上げます。
3月11日の震災以来、
テレビの映像にショックを感じ、被災者の言葉に涙し、何かに付け合掌して
祈らずにはいられない毎日でした。
しばらくの間、家を出る気にもなれず、ブログの更新することも出来なかった。
これまでに経験したことのない未曾有の被害と,
それを直接経験した人々の心の傷は計り知れないものがあることは
想像するに余りあります。
どうか一日でも早く、少しでも以前の生活に近づくようにお祈り申し上げます。
「今私達に出来ること・・・・」
考えながら生活してゆきますが、これから今までの価値観を変えなくてはならない
ことはいうまでもなく、これほどまでの犠牲を払い私達に警鐘を
与えてくれたことが何かを考える時が来ているのだと思います。
親戚のタンゲナ鈴木由香里さん。
ご家族は森町の出で、清水に住んでいたこともありました。
以前「母への讃歌」と言う本の翻訳をしてこのブログでも紹介しました。
由香里さんは、オランダのエイントホーフェンというところに住んでいて、
教会を通して色々な活動をしています。
この度の東日本大震災のチャリティーコンサートをふたつの町で呼びかけました。

以下に紹介します。
<オランダの小さな村から>
オランダの南の端に位置し、3万人ほどが住むファルケンスワールドという村で、
4月3日に300人ほどの人たちが集まり、東日本大震災の犠牲者のために、
追悼音楽会が開かれ、義援金も、1,523.20ユーロが集まった。
ほとんどの催しが、現地に住む日本人が主導で開催される中で、
今回の集まりは、現地の人々が立ち上がって、日本人のために集まるという
とてもユニークなものだった。
会場では、共に犠牲者を想って祈りをささげ、音楽を聴きながら、
自分たちの想いを日本という地球の反対側にある国に馳せた。
近辺に住む私たち日本人も、自分ができることをさせてもらいたいと、
さまざまなところで力をあわせて協力した。
2011年3月11日、突然日本を襲った巨大地震と津波は、海外に住む
私たちの目をインターネットテレビに釘付けにし、心を麻痺させてしまった。
その後、感じた無力感と深い深い悲しみは、今までに経験したことの無い
ものだった。
さらに、原子力発電所の事故のため、いまだに、いつ終わるともわからない、
不安な思いにさらされている。
このことを通して、自分を改めて日本人と意識した者も多かった。
災害の後、メディアは競って日本人の秩序正しさと助け合いの精神を
絶賛した。これは海外に住む私たちにも大きな力を与えてくれた。
そんな中でのオランダ人たちの暖かな支援は、とりもなおさず現地に住む
私たちへの支援でもあった。
画像の前でただただ嗚咽していた者を立ち上がらせてくれた。
たとえ被害に遭われた方の苦しみの一パーセントも理解できなくても、
私たちもこの方々のために何かできることはないだろうか、
という想いに駆られていった。
30年前は、私が日本人とわかると、大戦中にインドネシアの日本軍収容所で
起こった残酷な話を聞かされた。
日本人が隣に引っ越してくると言って、別のところに引っ越された人もあった。
それが、今は私が日本人だと分かると、家族は大丈夫か、と心配そうに聞いてくる。
三十年の歳月を思うと同時に、いつもは取り澄まして見える
オランダ人の思いやりの深さ、絆を大切にする暖かな心を心行くまで
感じさせてもらった。
(タンゲナ鈴木由香里 2011年4月4日)
<プログラム>


みなさま
4月3日の追悼コンサートはおかげさまで大成功をおさめました。
本当に神様がすべてを整えてくださったという想いにさせられております。
どうぞ、オランダからのメッセージを受け取ってください!
それぞれ、自分のおかれた場所で、何ができるか継続的に考えて
いきたいと思っております。
由香里
3月11日の震災以来、
テレビの映像にショックを感じ、被災者の言葉に涙し、何かに付け合掌して
祈らずにはいられない毎日でした。
しばらくの間、家を出る気にもなれず、ブログの更新することも出来なかった。
これまでに経験したことのない未曾有の被害と,
それを直接経験した人々の心の傷は計り知れないものがあることは
想像するに余りあります。
どうか一日でも早く、少しでも以前の生活に近づくようにお祈り申し上げます。
「今私達に出来ること・・・・」
考えながら生活してゆきますが、これから今までの価値観を変えなくてはならない
ことはいうまでもなく、これほどまでの犠牲を払い私達に警鐘を
与えてくれたことが何かを考える時が来ているのだと思います。
親戚のタンゲナ鈴木由香里さん。
ご家族は森町の出で、清水に住んでいたこともありました。
以前「母への讃歌」と言う本の翻訳をしてこのブログでも紹介しました。
由香里さんは、オランダのエイントホーフェンというところに住んでいて、
教会を通して色々な活動をしています。
この度の東日本大震災のチャリティーコンサートをふたつの町で呼びかけました。

以下に紹介します。
<オランダの小さな村から>
オランダの南の端に位置し、3万人ほどが住むファルケンスワールドという村で、
4月3日に300人ほどの人たちが集まり、東日本大震災の犠牲者のために、
追悼音楽会が開かれ、義援金も、1,523.20ユーロが集まった。
ほとんどの催しが、現地に住む日本人が主導で開催される中で、
今回の集まりは、現地の人々が立ち上がって、日本人のために集まるという
とてもユニークなものだった。
会場では、共に犠牲者を想って祈りをささげ、音楽を聴きながら、
自分たちの想いを日本という地球の反対側にある国に馳せた。
近辺に住む私たち日本人も、自分ができることをさせてもらいたいと、
さまざまなところで力をあわせて協力した。
2011年3月11日、突然日本を襲った巨大地震と津波は、海外に住む
私たちの目をインターネットテレビに釘付けにし、心を麻痺させてしまった。
その後、感じた無力感と深い深い悲しみは、今までに経験したことの無い
ものだった。
さらに、原子力発電所の事故のため、いまだに、いつ終わるともわからない、
不安な思いにさらされている。
このことを通して、自分を改めて日本人と意識した者も多かった。
災害の後、メディアは競って日本人の秩序正しさと助け合いの精神を
絶賛した。これは海外に住む私たちにも大きな力を与えてくれた。
そんな中でのオランダ人たちの暖かな支援は、とりもなおさず現地に住む
私たちへの支援でもあった。
画像の前でただただ嗚咽していた者を立ち上がらせてくれた。
たとえ被害に遭われた方の苦しみの一パーセントも理解できなくても、
私たちもこの方々のために何かできることはないだろうか、
という想いに駆られていった。
30年前は、私が日本人とわかると、大戦中にインドネシアの日本軍収容所で
起こった残酷な話を聞かされた。
日本人が隣に引っ越してくると言って、別のところに引っ越された人もあった。
それが、今は私が日本人だと分かると、家族は大丈夫か、と心配そうに聞いてくる。
三十年の歳月を思うと同時に、いつもは取り澄まして見える
オランダ人の思いやりの深さ、絆を大切にする暖かな心を心行くまで
感じさせてもらった。
(タンゲナ鈴木由香里 2011年4月4日)
<プログラム>


みなさま
4月3日の追悼コンサートはおかげさまで大成功をおさめました。
本当に神様がすべてを整えてくださったという想いにさせられております。
どうぞ、オランダからのメッセージを受け取ってください!
それぞれ、自分のおかれた場所で、何ができるか継続的に考えて
いきたいと思っております。
由香里
2011年02月23日
”春色の本たち”折金製本工房の作品展
1月27日から2月23日まで「折金製本工房」生徒の作品展が開かれました。
今回は折金先生が100人の人から募集した絵で「豆本」を100冊作り
展示しました。にぎやかな展示でしたのでご紹介します。
下は春色のプリントで作った私めの装丁作品です。

で,展示作業の会場の様子。
100人の絵を100冊の豆本にして空中に吊るして展示作業をしました。

かわいい絵本たち

小さな絵本もたくさん作ってありました

かわいいプリントのアルバムです。お祝いに良いですね。


輸入の壁紙を利用した本を作った生徒さんの作品

先生の豆本です。ブランドの包装紙などで作って素敵です。


この陳列は切り株を利用した陳列台です。雰囲気が出ます。

またやりますので是非ごらんになってください。
今回は折金先生が100人の人から募集した絵で「豆本」を100冊作り
展示しました。にぎやかな展示でしたのでご紹介します。
下は春色のプリントで作った私めの装丁作品です。

で,展示作業の会場の様子。
100人の絵を100冊の豆本にして空中に吊るして展示作業をしました。

かわいい絵本たち

小さな絵本もたくさん作ってありました

かわいいプリントのアルバムです。お祝いに良いですね。


輸入の壁紙を利用した本を作った生徒さんの作品

先生の豆本です。ブランドの包装紙などで作って素敵です。


この陳列は切り株を利用した陳列台です。雰囲気が出ます。

またやりますので是非ごらんになってください。
2010年12月26日
色々なご報告
約一月のご無沙汰更新です。
ごくごくこちらのローカルな表現の仕方で「やるせがない」
状態でした。つまり、色々次から次にやる事が出て来て、
めまぐるしい状態・・・・とでもいうのでしょうか。
ここでいちどにご報告。
ビックサイトで行なわれたJAPANTEXと同時開催のインテリアフェスティバルに
全国のインテリアデザイナー、コーディネーターさん達に混じり、パネル展示させて
頂きました。全国の皆さん、とてもすばらしい活躍をされていて、
啓発されました。ビジュアルの大切さを知りました。


恥ずかしながら・・・・

12/5、バーズにてクリスマスリースのワークショップが開催されました。

それはもう大にぎわい。午前と午後とも皆さん立派なリースを作ってお帰りになられました。

有名なお料理の「I」先生も参加くださいました。素敵でした。

12/11〜19はまたまたギャベ展。今回で3回目です。

100枚ほどのギャベが勢揃い。

前回お買い上げの客様のお話ですと、
「この最高に暑い夏にどうかなと思っていたのに、純毛のギャベが意外にも
ひんやりとしていて気持ちがよかった。40°以上にもなる地方で長い年月の間に
培われて来たギャベが人々の命を守るのに一役買って来た事が
納得出来ました。」
とおっしゃっていました。化学繊維のカーペットでは熱がこもってしまうところ
純毛の威力を感じさせるお言葉でした。
小さなギャベは使い方それぞれで、小さなお子様に人気がありました。

ごくごくこちらのローカルな表現の仕方で「やるせがない」
状態でした。つまり、色々次から次にやる事が出て来て、
めまぐるしい状態・・・・とでもいうのでしょうか。
ここでいちどにご報告。
ビックサイトで行なわれたJAPANTEXと同時開催のインテリアフェスティバルに
全国のインテリアデザイナー、コーディネーターさん達に混じり、パネル展示させて
頂きました。全国の皆さん、とてもすばらしい活躍をされていて、
啓発されました。ビジュアルの大切さを知りました。


恥ずかしながら・・・・

12/5、バーズにてクリスマスリースのワークショップが開催されました。

それはもう大にぎわい。午前と午後とも皆さん立派なリースを作ってお帰りになられました。

有名なお料理の「I」先生も参加くださいました。素敵でした。

12/11〜19はまたまたギャベ展。今回で3回目です。

100枚ほどのギャベが勢揃い。

前回お買い上げの客様のお話ですと、
「この最高に暑い夏にどうかなと思っていたのに、純毛のギャベが意外にも
ひんやりとしていて気持ちがよかった。40°以上にもなる地方で長い年月の間に
培われて来たギャベが人々の命を守るのに一役買って来た事が
納得出来ました。」
とおっしゃっていました。化学繊維のカーペットでは熱がこもってしまうところ
純毛の威力を感じさせるお言葉でした。
小さなギャベは使い方それぞれで、小さなお子様に人気がありました。

2010年10月31日
2010年10月24日
満開です
岡部のショールームの横は今、コスモスが満開です。
この写真は先々週の写真です。今もっと密度が濃くなって咲いています。



きばなコスモスは雑草のように強いのですが、上のピンクや赤のコスモスは
毎年交配してゆくと小さな花で、弱くなってゆくそうです。

今週がピークです。
そして今日はコスモス祭りです。皆さんコスモスを摘んでお帰りになられます。
この写真は先々週の写真です。今もっと密度が濃くなって咲いています。



きばなコスモスは雑草のように強いのですが、上のピンクや赤のコスモスは
毎年交配してゆくと小さな花で、弱くなってゆくそうです。

今週がピークです。
そして今日はコスモス祭りです。皆さんコスモスを摘んでお帰りになられます。
2010年08月13日
母への讃歌
一冊の本を紹介します。


「母への讃歌」
オランダ人 ヘンリエッテ・ファン・ラールテ・ヘール(著)
タンゲナ鈴木由香里(訳)
出版 いのちのことば社
ヘンリエッテ幼少の頃インドネシア在住のオランダ人が
戦中、日本軍抑留所に収容され、確実に飢餓の状態に
進行してゆく中で、収容所において彼女の母が
どのようにして命を守り続けて来たか、そしてその時の
記憶と,資料で綴られています。
戦争はどちらにとっても悲劇しか生みません。
大きな流れの戦争の歴史の隙間にこのような小さな歴史が
あったことを知る事が出来ました。
私がヨーロッパに住んでいた頃はオランダ人との交流は
ごく少なかった為に、とても友好的に接してくれた事しか記憶がなく、
それ以外の事は聞きづてのことしかわかりません。
友人のからは、ちょっと非友好的な言葉をかけられた事も聞きました。
しかし「無知の罪」は免れませんでした。いつか聞いた
「日本とオランダの関係は戦中インドネシアにおいては良好だった」
という、インフォメーションが私の心に存在してしまっていたから。
訳のタンゲナ・鈴木由香里さん。遠縁の親戚にあたり
私がケルンメッセを訪れた折り、ケルンから列車を乗り継いで
エイントホーフェン近くの由香里さんの自宅を訪問しました。
クリスチャンである由香里さんは、長年教会のボランティアの
仕事を熱心に務め、その国やコミュニティーに貢献して来ました。
そして心を許し合ったヘンリエッテの著書の日本語訳をしました。
この時期だからこそ、この本を皆さんに紹介したいと思いました。
戦争は理屈無しに多くの犠牲を伴います。
そうした犠牲の上に今の私達の生活がある事を忘れてはいけないと
思いましたし、知られていない小さな歴史物語をも胸に受け止めて
行かなければならないと思いました。
以下に書評を掲載させていただきます
GOSPEL INFORMATION ブックレビュー
日本軍政下を生きた、母と娘の真実
木村公一(福岡国際キリスト教会牧師)
前部分略・・・・
・・・飢餓と病気が支配する状況のもとで多くの収容者が死んでいった。
絶望的な日々の中 で、なおも生き抜くことを教えてくれたのは、賢くも
勇敢な母親であった。抑留所長タナカによって課せられた懲罰や恐怖
に対しても、母は希望と信仰と愛に よって向き合った。ヘンリエッテは、
オランダ人の苦難だけでなく、インドネシア人の苦難にも触れている。
さらに、日本への訪問を通して、戦争に翻弄された 日本の民衆の苦し
みにも共感する。だがこの本を読む現代の日本人は、過去の歴史と向
き合い、オランダ人抑留者たちに加えられた暴力を記憶することによっ
て、《戦後責任》を自覚することになる。この書は二十一世紀を生きる
成熟した日本人を造り上げる最良の教科書の一冊となるであろう。
最後に、素晴らしい訳 文に仕上げてくださった訳者の
タンゲナ鈴木由香里さんに感謝を申し上げたい。


「母への讃歌」
オランダ人 ヘンリエッテ・ファン・ラールテ・ヘール(著)
タンゲナ鈴木由香里(訳)
出版 いのちのことば社
ヘンリエッテ幼少の頃インドネシア在住のオランダ人が
戦中、日本軍抑留所に収容され、確実に飢餓の状態に
進行してゆく中で、収容所において彼女の母が
どのようにして命を守り続けて来たか、そしてその時の
記憶と,資料で綴られています。
戦争はどちらにとっても悲劇しか生みません。
大きな流れの戦争の歴史の隙間にこのような小さな歴史が
あったことを知る事が出来ました。
私がヨーロッパに住んでいた頃はオランダ人との交流は
ごく少なかった為に、とても友好的に接してくれた事しか記憶がなく、
それ以外の事は聞きづてのことしかわかりません。
友人のからは、ちょっと非友好的な言葉をかけられた事も聞きました。
しかし「無知の罪」は免れませんでした。いつか聞いた
「日本とオランダの関係は戦中インドネシアにおいては良好だった」
という、インフォメーションが私の心に存在してしまっていたから。
訳のタンゲナ・鈴木由香里さん。遠縁の親戚にあたり
私がケルンメッセを訪れた折り、ケルンから列車を乗り継いで
エイントホーフェン近くの由香里さんの自宅を訪問しました。
クリスチャンである由香里さんは、長年教会のボランティアの
仕事を熱心に務め、その国やコミュニティーに貢献して来ました。
そして心を許し合ったヘンリエッテの著書の日本語訳をしました。
この時期だからこそ、この本を皆さんに紹介したいと思いました。
戦争は理屈無しに多くの犠牲を伴います。
そうした犠牲の上に今の私達の生活がある事を忘れてはいけないと
思いましたし、知られていない小さな歴史物語をも胸に受け止めて
行かなければならないと思いました。
以下に書評を掲載させていただきます
GOSPEL INFORMATION ブックレビュー
日本軍政下を生きた、母と娘の真実
木村公一(福岡国際キリスト教会牧師)
前部分略・・・・
・・・飢餓と病気が支配する状況のもとで多くの収容者が死んでいった。
絶望的な日々の中 で、なおも生き抜くことを教えてくれたのは、賢くも
勇敢な母親であった。抑留所長タナカによって課せられた懲罰や恐怖
に対しても、母は希望と信仰と愛に よって向き合った。ヘンリエッテは、
オランダ人の苦難だけでなく、インドネシア人の苦難にも触れている。
さらに、日本への訪問を通して、戦争に翻弄された 日本の民衆の苦し
みにも共感する。だがこの本を読む現代の日本人は、過去の歴史と向
き合い、オランダ人抑留者たちに加えられた暴力を記憶することによっ
て、《戦後責任》を自覚することになる。この書は二十一世紀を生きる
成熟した日本人を造り上げる最良の教科書の一冊となるであろう。
最後に、素晴らしい訳 文に仕上げてくださった訳者の
タンゲナ鈴木由香里さんに感謝を申し上げたい。
2010年06月02日
製本作品展&ワークショップ
6/14まで掛川駅構内、アトリエ処にて「折金製本工房作品展」&
ワークショップを開催しています。
恥ずかしながら,私も出品しています。


いつものように、行き当たりばったりの布ディスプレイで高さを作りましたが、
肝心の作品は初日に間に合わなくて、私の作品は三日目から展示させて
いただきました。

今回は、フランス・プロヴァンス地方のプリント生地『ソレイアード』と
『ウィリアム・モリス』の生地を主に使い製作しました。
壁に立てかけてあるものは、ワインボトルカバー。
『ソレイアード』ではないのですが、プロヴァンスの生地を使い
縫いました。
『ソレイアード』の生地のものは、本とお揃いでプレゼントにもなります。

製本は私の場合、今のところは全てハードカバーを製作しているので、
ディテールは下のようになります。

また、少しですが『ウィリアム・モリス』を使い作ったノートと
同じ生地で縫製したクッションも出品してあります。

下の写真は先生が作られた、豆本です。と,言っても立派に
行程は大きな本と同じ。
インテリアアクセサリーとして、今ちょっとブームになっているようです。

で、豆本などのワークショップを行ないますので、興味のある方は
是非お出かけください。
****製本ワークショップ****
★ 本の修理の実験
5/31(月)13:30〜15:30 (すみません,もう終了ですが参考までに)
講師:折金先生
受講料:¥500
糸綴じの絵本を解体して,綴じ直します。
★ 簡易アルバムの改装
6/3(水)13:30〜16:00
講師:平松激人
受講料:¥500
簡易アルバムをハードカバーのおしゃれなアルバムに改装します。
★ 豆本を作りましょう
6/10(水)13:30〜14:30
講師:折金先生
受講料:¥500
小さいかわいい白い本を作ります。
お申し込みはレジの方にお願いします。
材料などは全てそろえてあります。
ワークショップを開催しています。
恥ずかしながら,私も出品しています。


いつものように、行き当たりばったりの布ディスプレイで高さを作りましたが、
肝心の作品は初日に間に合わなくて、私の作品は三日目から展示させて
いただきました。

今回は、フランス・プロヴァンス地方のプリント生地『ソレイアード』と
『ウィリアム・モリス』の生地を主に使い製作しました。
壁に立てかけてあるものは、ワインボトルカバー。
『ソレイアード』ではないのですが、プロヴァンスの生地を使い
縫いました。
『ソレイアード』の生地のものは、本とお揃いでプレゼントにもなります。

製本は私の場合、今のところは全てハードカバーを製作しているので、
ディテールは下のようになります。

また、少しですが『ウィリアム・モリス』を使い作ったノートと
同じ生地で縫製したクッションも出品してあります。

下の写真は先生が作られた、豆本です。と,言っても立派に
行程は大きな本と同じ。
インテリアアクセサリーとして、今ちょっとブームになっているようです。

で、豆本などのワークショップを行ないますので、興味のある方は
是非お出かけください。
****製本ワークショップ****
★ 本の修理の実験
5/31(月)13:30〜15:30 (すみません,もう終了ですが参考までに)
講師:折金先生
受講料:¥500
糸綴じの絵本を解体して,綴じ直します。
★ 簡易アルバムの改装
6/3(水)13:30〜16:00
講師:平松激人
受講料:¥500
簡易アルバムをハードカバーのおしゃれなアルバムに改装します。
★ 豆本を作りましょう
6/10(水)13:30〜14:30
講師:折金先生
受講料:¥500
小さいかわいい白い本を作ります。
お申し込みはレジの方にお願いします。
材料などは全てそろえてあります。
2010年02月13日
カーニバル(アルマニッシュファッシング)

冬期オリンピックも始まり、そして
カーニバルの季節がやって参りました。
いきなり恐い写真でごめんなさい。
私がドイツ滞在中に経験したカーニバルです。
このとき私はフライブルクからハンブルクに移り住んでいましたが、
どうしてもこの地方のカーニバルが見たくて、北の端から
南のこの街に帰って来ました。
これは、南ドイツ黒い森地方:フライブルク近郊の
エルザッハというところのカーニバルの様子です。
ドイツでは「ファスナハト」「ファッシング」と呼ばれています。
このフライブルクの周辺のカーニバルは、ドイツがキリスト教化される
以前のゲルマンの古い習慣と民間信仰の名残りが顕著に見られる
ドイツの民俗学に興味があれば絶対に見逃してはいけないと
(そう確信しているのは私だけかも知れませんが・・・)思われる
カーニバル:ファッシングです。


このエルザッハというところのファッシングが面白いと聞き
しかも夜は見物だからという事で行ってみると、
なんと街についたとたんに、建物の影からこんな恐い顔を
した人がぴょんぴょんスキップしながら出て来て、
なにかで、あっちこっちビタビタ叩きまくっているのではありませんか。
これ水の入った「ブタの膀胱」なんです。
そして頭にかぶっているのは、よく見ると麦わら帽子を
まくり上げ、エスカルゴが、びっしりと貼付けられている、
不思議な帽子です。
何とも驚きというかショッキングな、それでいて、赤い服が可愛くて
スキップしているその姿は、全ての要素がミスマッチで幻想的な
雰囲気でした。
これは、冬を追い払い春を呼ぶ祭りとしての意味が込められている
仮面の奇祭と呼ばれています。
この奇妙な人達は「ナロ」とよばれていて、
(馬鹿者などという意味らしい)
次の日にはここで一番大きな街フライブルクでナロの
カーニバルがあるのです。
その様子は以下の写真で。それぞれの村々によって
仮装が違います。
これらを見ていると、森と共に生きて来た民族の様子を
うかがう事が出来ます。






カーニバルは本来、復活祭の前の40日をキリストの受難を思って
肉食を断ち、禁欲生活を営む四旬節に入る直前に、
たらふくごちそうを食べて、仮装行列などで大騒ぎをする祭りです。
ベネチアやニースなどは有名ですね。
ドイツではケルンなどのカーニバルが有名で、前にも述べたように
「ファスナハト」「ファッシング」などとよばれ仮装行列や舞踏会が
盛大に行われます。
2010年01月30日
製本工房Origane:グループ展

製本工房Origane グループ展に出品しました。

まず、会場作りから。カーテン生地でディスプレイ。
条件が限られていますので、なかなか現場に行ってその時の感覚で
やってみるしかありません。
ディスプレーが終わって急いで帰って来てしまい、先生の作品を
写して来れませんでした。すみません!
下は私の作品。
ペアの製本ノートにおリボンをして、プレゼント用に。
ばら売りのものもあります。

そして、中畑さんの作品。
可愛い豆本のペンダントがトルソーにかかっています。

ちなみにどんなものかをいくつか紹介します。




可愛い生地や美しい布を見つけるとなぜか「製本出来るかどうか」に考えが
はしってしまうこのごろ。仕舞には着ている服にも
「これは製本の材料になるかなー・・・・」と目が行く。
そして、鋏を入れてしまうのも時間の問題かも知れません。
家にも布がたまって来ました。
困ったものです。
2010年01月14日
Please enjoy it!

オランダの友人から送られて来ました。
ただひたすら楽しんで下さい!
動画が動かない場合は
こちら
で画面のすべてが見られます。
リバプールストリート駅で
動画が動かない場合は
こちら
で画面のすべてが見られます。
アントワープ駅で
動画が動かない場合は
こちら
で画面のすべてが見られます。
終わった後のクールな散り方が面白いですね。
2009年06月24日
温泉レモネード
岡部町のスーパーで見つけました。

レトロなラベルに惚れ込んで、昭和生まれの私としましては
ついつい買わずにいられませんでした。
昔、縁日や駄菓子屋さんにあったラムネはレモネードが
訛ったものだそうです。ラベルの女性が外国人で,
レモネードとはなんとおしゃれでしょう。

説明書きには「昔、温泉地で療養や避暑を始めた外国人の間で
飲まれたものを・・・」というような事が書かれていました。
(ちゃんと覚えてくれば良かった・・・、そういえば軽井沢も
外国人が避暑地として開発したとか・・・)

温泉と書いてありますが読み方は「うんぜん」。
「雲仙温泉組合」
「TOMOMASU 創業明治35年」などの表示がありました。
なかなか粋なはからいですね。
この色合いといいデザインといい,昭和生まれのおじさま、
おばさまをターゲットにしたノスタルジックなパッケージデザインは
これからも登場しそうですね。

レトロなラベルに惚れ込んで、昭和生まれの私としましては
ついつい買わずにいられませんでした。
昔、縁日や駄菓子屋さんにあったラムネはレモネードが
訛ったものだそうです。ラベルの女性が外国人で,
レモネードとはなんとおしゃれでしょう。

説明書きには「昔、温泉地で療養や避暑を始めた外国人の間で
飲まれたものを・・・」というような事が書かれていました。
(ちゃんと覚えてくれば良かった・・・、そういえば軽井沢も
外国人が避暑地として開発したとか・・・)

温泉と書いてありますが読み方は「うんぜん」。
「雲仙温泉組合」
「TOMOMASU 創業明治35年」などの表示がありました。
なかなか粋なはからいですね。
この色合いといいデザインといい,昭和生まれのおじさま、
おばさまをターゲットにしたノスタルジックなパッケージデザインは
これからも登場しそうですね。
2009年06月08日
素敵な知らせ
ドイツに住んでいる友人(日本人女性で清水出身)の
息子さんが南ドイツで挙げた結婚式の様子を
写真構成して送ってくれました。なんかうっとり・・・。
まるでウェディングのカタログを見ているような気分。
そして,幸せ一杯の二人やご家族の様子にこちらまで幸せな
気持ちになりました。


南ドイツはカソリックの土地柄、教会の有る村からは伝統的な
楽隊もでてきますし、二人の結婚を祝うパーティーの
にぎやかさが伝わって来ます。
タロちゃん、ベアトリーチェ、おめでとう!お幸せに!
息子さんが南ドイツで挙げた結婚式の様子を
写真構成して送ってくれました。なんかうっとり・・・。
まるでウェディングのカタログを見ているような気分。
そして,幸せ一杯の二人やご家族の様子にこちらまで幸せな
気持ちになりました。


南ドイツはカソリックの土地柄、教会の有る村からは伝統的な
楽隊もでてきますし、二人の結婚を祝うパーティーの
にぎやかさが伝わって来ます。
タロちゃん、ベアトリーチェ、おめでとう!お幸せに!
2009年02月21日
手製本の贈り物展
3月2日まで、掛川駅のコンコース「これしか処ギャラリー」にて、
冬の贈り物展の一角に、折金紀男先生と製本工房お仲間の皆さんが
作った装丁本、ブックカバーオリジナルノートなどの展示即売会が
開かれています。

素敵な布の表紙でオリジナルのノートが作られています。

装丁家の折金先生がロシアに行かれた際のパスポートも思い出として
本の表紙になってしまいました。

和綴じ本の「源氏物語」と素敵な装丁の本

こんなノートにお料理のレシピを書いたら楽しいですね。

カルトナージュに入った本たち。

そして、恥ずかしながら私の書いた教室のノートまでもが
展示物になっていました。


「ノートの中に自分のすべてがある
ノートの中に自分を閉じ込めるのではなくて
ノートの中に自分を解き放つ
そんなノートを作りたい」折金紀男
先生、いつまでも素敵な装丁本制作や、貴重な古い本の修理で
再び本に命を吹き込む魔法を続けて下さい。
冬の贈り物展の一角に、折金紀男先生と製本工房お仲間の皆さんが
作った装丁本、ブックカバーオリジナルノートなどの展示即売会が
開かれています。

素敵な布の表紙でオリジナルのノートが作られています。

装丁家の折金先生がロシアに行かれた際のパスポートも思い出として
本の表紙になってしまいました。

和綴じ本の「源氏物語」と素敵な装丁の本

こんなノートにお料理のレシピを書いたら楽しいですね。

カルトナージュに入った本たち。

そして、恥ずかしながら私の書いた教室のノートまでもが
展示物になっていました。


「ノートの中に自分のすべてがある
ノートの中に自分を閉じ込めるのではなくて
ノートの中に自分を解き放つ
そんなノートを作りたい」折金紀男
先生、いつまでも素敵な装丁本制作や、貴重な古い本の修理で
再び本に命を吹き込む魔法を続けて下さい。
2008年12月31日
薪ストーブ

先日も新聞に載っていましたが、薪ストーブが売れているのだそうです。
家具ショールーム・バーズにもアメリカ・バーモントキャスティングの
薪ストーブに火を入れています。
いたずら心で焼きリンゴに挑戦。ワイルドに行こうと思います。
第一回目は、丸ごとホイルに包んで、鉄のフライパンを乗せ、
それに置いてみました。いい臭いがショールームに漂います。
ところが、あまりの高熱で、したの方だけが解けたようになりました。
簡単に考えていたのですが・・・

そこで、後日、均等に火が行き届くようにフライパンの上にやはりホイルを敷いて、
切ったリンゴを並べてストーブに乗せました。

今度は成功。火が通ったと確認したところで、グラニュー糖と
シナモンをふりかけ、ハイおやつの出来上がり。
年末のひとときでした。
皆様、良いお年をお迎えくださいね。
2008年12月02日
色々なご報告(4)伝統的なもの

前回記事のお世話になった京人形屋さんの後継者のお兄さん。
住まいをを三条平安神宮近くに移し、以前と変わらず伝統的な
京人形を製作しています。今は季節的に干支のもので忙しいのですが、
新しい形の京人形も意欲的に作っています。

ただ、伝統産業の現場は大変厳しく、このご時世に削るところは
こういう分野のものがどんどん削られてゆく時代だそうで、
「こういう人形の分野は、もうあかんなぁー。昔と様子が違う
さかいになぁー・・・それに、ええ人形を作るもんがいなく
なったしなぁー・・・」ということでした。
新しくデザインしたひな人形も見せて下さいました。
又追ってご紹介しますがそのディテールだけでも拡大して
お見せしましょう。

フォルムの美しさもさることながら、衣の柄も一筆一筆描いている
気の遠くなるような仕事です。
がんばってなんとかこのすばらしい感性と技術を伝えていって
欲しいものです。
古い友人達にも会いました。
ロケーションがまたすばらしいお庭でした。
「桜鶴苑」という南禅寺近くの個人の邸宅だったところです。


そのお庭は芸術的でした。
土地の高低をなだらかな流れにして、大切に大切に苔を維持しています。
石の並びもどの角度からも自然な感じでかつ計算され尽くしてあり、
思わず呆然と立ち尽くしてしまいました。
近年私の訪れたお庭の中では最も驚くべき点の多いお庭でした。
すばらしいの一言でした。
お料理もすばらしい京懐石。

一つ一つが宝石のようでした。
今回の京都はお見舞いが目的でしたが、短いなりにも「心の旅」でした。
2008年12月02日
色々なご報告(3)お見舞い
両親と親交の深かった京都府宮津のMさんご家族のお母様、
そして京都市内の知人のお見舞いに11月初旬、行って参りました。


宮津の天橋立の付け根にあるお家のまわりは、古い町並みや丹後の縮緬の里、
少し車を走らせると舟屋(ふなや)で有名な伊根町というところがあります。
海側から見た遠景。

近くから見た様子。

そして裏側の街道から見た舟屋の様子。

なんと、海側から見たのとは違い、お蔵のような作りをしています。
地元のおばあちゃんから聞いた話ですと、
舟屋には若夫婦が住み、道を挟んだ母屋には老夫婦が住むのがしきたりなのだそうです。
静かなたたずまいのこの町ももう今では雪が降り、
厳しい冬が来ているとの事です。
どうぞ、御体大切に。この次にお伺い出来るならば、
以前のようにお元気になられていらっしゃる事、
お祈りしています。
そして京都市内の知人のお見舞いに11月初旬、行って参りました。


宮津の天橋立の付け根にあるお家のまわりは、古い町並みや丹後の縮緬の里、
少し車を走らせると舟屋(ふなや)で有名な伊根町というところがあります。
海側から見た遠景。

近くから見た様子。

そして裏側の街道から見た舟屋の様子。

なんと、海側から見たのとは違い、お蔵のような作りをしています。
地元のおばあちゃんから聞いた話ですと、
舟屋には若夫婦が住み、道を挟んだ母屋には老夫婦が住むのがしきたりなのだそうです。
静かなたたずまいのこの町ももう今では雪が降り、
厳しい冬が来ているとの事です。
どうぞ、御体大切に。この次にお伺い出来るならば、
以前のようにお元気になられていらっしゃる事、
お祈りしています。